| > | CTI Label | ||||||
| CTI Label CTI レーベル |
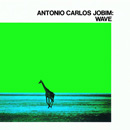 |
||||
|
1967- 1978 レコード・レーベル
2011(H23)年05月掲載 |
||||
| Wave /Antonio Carlos Jobim 1967 | ||||||
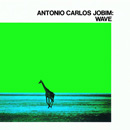 |
||||||
|
LP:
・A&M SP 3002 (1967) ・A&M SP-9-3002 (1967) CD: |
||||||
|
Ron Carter(Acoustic Bass)、
Domum Romao(Drums)、Bobby Rosengarden(Drums)、Claudio Slon(Drums)、 Joseph Singer(French Horn)、 Ray Beckenstein(Flutes & Piccolo)、Romeo Penque(Flutes & Piccolo)、Jerome Richardson(Flutes & Piccolo)、 Urbie Green(Trumborn)、Jimmy Cleveland(Trumborn)、 Antonio Carlos Jobin(Piano, Guitar & Harpsichord)、 Conductor: Claus Ogerman(クラウス・オガーマン) Violins: Bernard Eichen、Lewis Eley、Paul Gershman、Emanuel Green、Louis Haber、Julius Held、Leo Kruczek、Harry Lookofsky、Joseph Malignaggi、Gene Orloff、Raoul Poliakin、Irving Spice、Louis Stone、 Cell: Abe Kessler、Charles McCracken、George Ricci、Harvey Shapino、 録音:Van Gelder Studios(アメリカ・ニュージャージー)、1967年5〜6月 |
||||||
| Tide /Antonio Carlos Jobim 1970 | ||||||
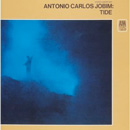 |
||||||
|
Tide(邦題:潮流)
LP: ・A&M SP 3031 (1970) ・A&M SP-9-3031 (1970) CD: |
||||||
|
Antonio Carlos Jobin(アントニオ・カルロス・ジョビン、Guitar、Piano、Electric Piano)、
Jerry Dodgion(ジェリー・ドジオン、Alto Sax solo on "Girl From Ipanema")、 Joe Farrell(ジョー・ファレル、Bass Flute solo on "Carinhoso" & "Caribe"、Soprano Sax solo on "Caribe")、 Hermeto Pascoal(エルメート・パスコアール、Flute solo on "Tema Jazz")、 Ron Carter(ロン・カーター、Acoustic Bass)、 Urbie Green(アービー・グリーン、Trumborn)、Joao Palma(ジョアン・パルマ、Drums)、Airto Moreira(アイアート・モレイラ、Perc)、 Eumir Deodato(エウミール・デオダート、Piano、Arrange、Conductor)、 録音:1970年3〜5月 |
||||||
| Prelude /Deodato 1972 | ||||||
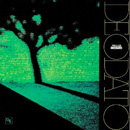 |
||||||
|
Prelude(邦題:ツァラトゥストラはかく語りき)
LP: ・A&M SP 3031 (1970) ・A&M SP-9-3031 (1970) CD: |
||||||
|
Arranged and Conducted by Eumir Deodato
Eumir Deodato(エウミール・デオダート、Piano、Electric Piano)、 John Tropea(ジョン・トロペイ、Electric Guitar 、solo on "1、4、6")、 Ron Carter(ロン・カーター、Acoustic Bass、Electric Bass on "4")、 Stan Clarke(スタンリー・クラーク、Electric Bass、solo on "1")、 Jay Berliner(ジェイ・バーリナー、Electric Guitar)、 Billy Cobham(ビリー・コブハム、Drums)、 Airto Moreira(アイアート・モレイラ、Perc)、 Ray Barretto(レイ・バレット、Conga)、 Trumpet: John Frosk、Marky Markowitz、Joe Shepley、Marvin Stamm(solo on "5")、 Trumborn: Wayne Andre、Garnett Brown、Paul Faulise、George Strakey、Bill Watrous French Horn: Jim Buffington、Peter Gordon Flute / Alto Flute / Bass Flute: Hubart Laws(ヒューバート・ロウズ、solo on "5")、Phil Bodner、George Marge、Romeo Penque Violin: Max Ellen、paul Gershman、Emanuel Green、Harry Lookofsky、David Nadien、Gone Orloff、Elliot Rsoff Viola: Al Brown、Emanuel Vardi Cello: Seymour Barab、Chales McCracken、Harvey Shapiro 録音:Van Gelder Studios(アメリカ・ニュージャージー)、1972年9月 |
||||||
| Deodato 2 /Deodato 1973 | ||||||
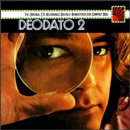 |
||||||
|
邦題:ラプソディー・イン・ブルー(エウミール・デオダート)
LP: ・CTI 6029 (1973) CD: |
||||||
|
録音:1973年5月 Englewood Cliffs, New Jersey
Producer:Creed Taylor Engineer:Rudy Van Gelder Eumir Deodato(Key、Arrange、Cond)、 Horns: Strings: 日本盤 LP/CD曲目(全5曲) 海外盤 LP/CD曲目(全8曲) CTIレーベルにおける、Eumir Deodato 氏(エウミール・デオダート、ブラジル出身、1943 - )のリーダー2作目。 このアルバムも70年代クロスオーバー黎明期を代表する不朽の大傑作アルバムです。 (CTIレーベルの創立者 Creed Taylor 氏のプロデュース) 作風は前作「Prelude」の流れをくむもので、デオダート氏自身による曲の他、クラシックの名曲をカバーしています。 名演奏が揃っており、中でも特に「Skyscrapers」「Super Strut」「Rhapsody In Blue」の3曲は音楽ファンの間でも特に評価の高い名演奏で、このアルバムの評価を確固たるものにしています。 「Skyscrapers」「Super Strut」は自身による作曲・アレンジで、Deodato 氏の70年代を代表する名演奏であることに留まらず、ファンク色のある70年代クロスオーバーを代表する、と言っても良いような理想的な素晴らしい演奏です。 ガーシュイン作曲の「Rhapsody In Blue」は実に雄大で面白いアレンジ。 原曲では一番最初にクラリネットで演奏され、曲の途中でも何度か出てくる導入部が、このアルバムではファンクな演奏の一番最後に一度だけピアノソロで出てくるなどの工夫も凝らされています。 もともとこの曲はクラシックのオーケストラによる演奏でも指揮者によって実に様々なアレンジがある名曲のようですが、デオダート氏によるこのアルバムの個性あるアレンジも、発表から数十年経過すれども色褪せる事はないようです。 このアルバムにもミュージシャンが大量投入されていますが、ホーンやストリングスの人数が前作よりさらに増加、そのおかげか、このアルバムのストリングスの音色は前作以上に透明度と厚みを増しておりとても美しい。 また前作同様、ギターは John Tropea 氏、Bass/Drumsのリズムは Stanley Clarke 氏、Billy Cobham 氏が参加しており、強力なファンク色を出しています。 特に Billy Cobham 氏はこの頃、やはり新しい音楽的な試みを行っていた John McLaughlin 氏(Guitar)のバンド「Mahavishnu Orchestra(マハビシュヌ・オーケストラ)」でも歌心溢れる素晴らしい演奏を残しており、また、後の音楽シーンに与えた影響も実に大きく、彼の演奏はこの時期の(70年代初め頃の)クロスオーバー黎明期のサウンドを大きく特徴付けていたとも言えるのではないでしょうか。 何度聴いても何十年聴いても飽きがこない、本当に全てが素晴らしい大傑作アルバム。 音楽ファン必携です。 (2015年 8月) |
||||||
| Giant Box /Don Sebesky 1973 | ||||||
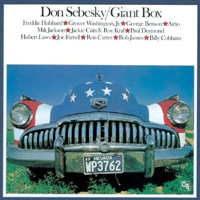 |
||||||
|
ドン・セベスキー
LP: ・CTX 6031/32 (1973) CD: |
||||||
| 録音:1973年4〜5月 Van Gelder Studios Producer:Creed Taylor Engineer:Rudy Van Gelder 1:Firebird(Igor Stravinsky)/Birds of Fire(John McLaughlin) 13:55
2:Song To A Seagull(Joni Mitchell) 5:50
3:Free As A Bird(Don Sebesky) 8:13
4:Psalm 150(Jim Webb) 8:11
5:Vocalise(Sergei Rachmaninoff) 5:40
6:Fly(Don Sebesky)/ Circles(Don Sebesky) 9:48
7:Semi-Tough(Don Sebesky) 7:52
Dave Friedman(Purcussion)、Phil Kraus(Purcussion) Horns and Woodwinds: Violin: Cello: Harp:Margaret Ross |
||||||
| ミュージシャンの参加数がもの凄い事になっている、Don Sebesky 氏(1937年 アメリカ生まれ・作曲・編曲・ピアノ演奏 他)の CTIレーベル における大作。 アナログLPで発表された当時は2枚組だったようです。 全曲のアレンジは Don Sebesky 氏によるもので、一部の曲でピアノ/Keyの演奏や、歌も披露しています。 もともとクラシックの素養があるアーティストのようで、このアルバムでは優雅で壮大なストリングスと、角の丸い大編成のブラス(ホーン)が大いに駆使されています。 Jazzがベースとなっている曲が多いと思いますが、クラシックやファンクなど、いろいろな要素が加わっていてまさにクロスオーバー、実験的な雰囲気も一部にあり個性豊かな曲が多いものの、全編通じて格調高い雰囲気で作風がまとめられている名作です。
1曲目「Firebird/Birds of Fire」はこのアルバムを大きく印象付ける実に雄大な名演奏。 クラシック曲、ストラヴィンスキーのバレエ組曲「Firebird(火の鳥)」のカバーとの事ですが、基本的には、John McLaughlin 氏 のバンド「Mahavishnu Orchestra(マハビシュヌ・オーケストラ)」の1973年「Birds of Fire(こちらも直訳が "火の鳥")」がベースで、そこにストラヴィンスキーの「Firebird」の導入部と最後のフルオーケストラ部分をくっつけた感じです。 しかし実に見事なアレンジの妙で、全く違和感なくとても自然につながっています。 John McLaughlin 氏 の作品と言えばベースとなっているのはジャズですが、当時もロックやファンクなどの要素がてんこ盛りの前衛的な作品が多く、それをクラシック曲とくっつけようとした Don Sebesky 氏の発想がそもそも凄い。 こんな凝った事をやっていたのだとわかった時はとても驚かされました。 ちなみに、Mahavishnu Orchestra 版の「Birds of Fire」は、同じ1973年発表のアルバム「Birds of Fire」(ただし録音は1972年9~11月)に収録されていますが、Drums が同じ Billy Cobham 氏によるファンクな演奏です。 どちらも実に見事な演奏なので聴き比べてみるととても面白いです。 |
|||
| Gambler's Life /Johnny Hammond 1974 | |||||||
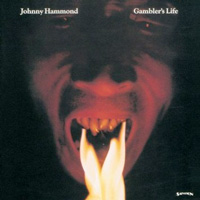 |
|||||||
|
LP:
・Salvation SAL-702 (1974) ・ CD: |
|||||||
|
Produced by Larry Mizell for Sky High Productions, Inc.
Arranged and Conducted by Larry Mizell Arranged by Johnny Hammond("This Year's Dream" ,"Virgo Lady") Synthesizer programmed by Chuck Davis Recorded at The Sound Factory, Hollywood, California, June 1974 Johnny Hammond Smith(Electric Piano、Synthesizer) Jerry Peters(Piano) Larry Mizell(Solina) Mel Bolton(Guitar)、Melvin "War War" Ragin(Guitar)、John Rowin(Guitae) Tony Dumas(Bass)、Henry Franklin(Bass) Harvey Mason(Drums)、Lritz Wise(Drums) King Errisson(Congas)、Stephanic Spruill(Oercussion、Vocals)、Carl Randall, Jr.(Saxophone)、Fonce Mizell(Clavinet、Trumpet)、Al Hall(Tromborne) Background Vocal/Vocal Arrangements:Larry Mizell、Fonce Mizell、Fred Perren 1:Gambler's Life(5:45) 2:Rhodesian Thoroughfare(6:06) 3:This Year's Dream(6:19) 4:Star Borne(7:51) 5:Back To The Projects(5:36) 6:Yesterday Was Cool(6:50) 7:Virgo Lady(6:41) 8:Call On Me(4:30) 70年代クロスオーバーの、どちらかと言えばまだ黎明期といえる1974年に、CTIレーベル 傘下の「サルヴェイション」というレーベルから発表された Johnny Hammond (Smith)(1933 - 1996)氏 のリーダー作。 オルガン奏者として1950〜60年代はジャズの分野で活躍、1971年以降はCTI傘下のCuduに移籍し、いわゆるクロスオーバー路線に本格参入した第1作目がこのアルバムとの事です。(2013年復刻CDのライナー解説:小川 充 氏) これまたライナー解説によると、ラリー・マイゼル、フォンス・マイゼルの兄弟による「スカイ・ハイ」というプロデュースチームは多くのジャズ・ミュージシャンを手掛けており、彼らがプロデュース・作曲・アレンジを行ったこのアルバムは近年評価が上がった名作との事です。 全ての曲が素晴らしく、アレンジや曲調が絢爛豪華なのが大きな特徴です。 Johnny Hammond 氏のエレピのソロは全編通じて饒舌で味わい深く、Harvey Mason 氏をはじめとする強力なリズム陣やファンクなカッティング・ギター、スマートなコーラスなど魅力が満載です。 Harvey Mason 氏のドラムフレーズは実に饒舌でグルーブ感が本当に素晴らしい。 アレンジに関しては、一つの曲の中でめまぐるしく曲調やリズムが変わることが多いのですが、いずれもセンスよくまとまっていて、絢爛豪華ながらもコテコテになる寸前で押さえているという絶妙さ。 しかも音の情報量・密度がとても高い印象なのに、繰り返し聴いても嫌にならない。 とにかく素晴らしい演奏が1曲目から続きます。 Johnny Hammond 氏自身がアレンジを行っているという7曲目「Virgo Lady」は、最初は3拍子のジャズで始まり、拍子や曲調がころころ変わりながら、最後はFM局のジングル風コーラスをバックにエレピのソロが流麗なバラードで終わるという意外な展開ですが、不思議とうまく魅力的にまとまっています。 後年(1975〜1976年)の Johnny Hammond 氏のリーダー作は、当時流行のディスコサウンドっぽい感じやポップさが増すような気がしますが、このアルバムはまだそこまでいっておらず、非常に良い案配。 また、このアルバムの作風は1976〜1977年頃の制作なら納得ですが、1974年時点でこの完成度と言うのはかなり時代を先取りしているような気がします。 その他、各種アナログ・シンセサイザーの音色が本当に美しく、特に3曲目「This Year's Dream」のソリーナの音色にはこの上ない幸福感を感じます。 70年代のアナログシンセの音色はなんて美しいのだろうとつくづく思います。 繰り返しになりますが、1974年にこれだけ完成度の高いクロスオーバーサウンドが出来上がっていたというのが本当に驚異です。 ジャズの要素に加え、ファンクやR&Bの要素、程よいさじ加減の70年代なポップさ、絢爛豪華なアレンジやシンセの音色、効果的なSE(効果音)、饒舌なソロや強力なリズム陣、ファンクなギターやパーカッションなど、個人的には「理想的な70年代クロスオーバー・サウンド」の要素がてんこ盛りという感想。 超おすすめ傑作アルバムです。 個人的には1〜3曲目が特にハマりました。 ただひとつ残念なのはホラー的なジャケットの写真で、アイディア/構図としては面白いのでしょうが、パッケージとしてはかなり損しているような気がします...。 (2015年 8月) |
|||||||
| > | CTI Label | |||||
|
! このホームページの画像・文章等はすべて転載禁止です。 |
|||||
|
||||